
|
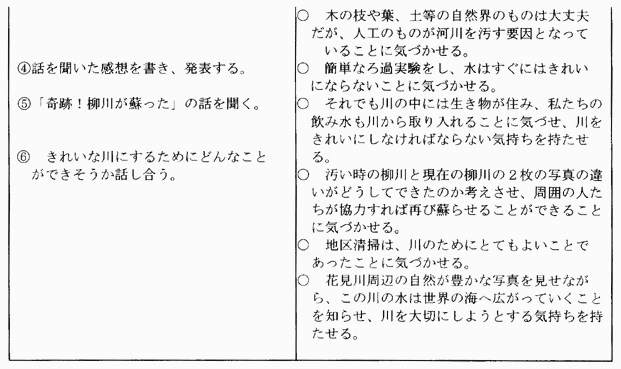
4 成果と課題
公園や地域の清掃など事前に取り組んできたいろいろな体験が、学習の中で子どもの発言として生きていました。また、これらの体験が共通の基盤となり、話し合いも活発になりました。
水槽が次第に汚れていくシミュレーションは、充分に子どもの興味・関心を弓1きつけるものでしたじ河川が汚れていくイメージが広がり、自分たちの問題としてとらえることができました。体験することは頭で理解するよりずっと印象的であり、自然な形で意識が高まってくることと思われます。
柳川の資料は、「川を汚したのは人間だが、きれいにするのも人間だ。」という気持ちを持たせるには効果的でした。
本時の学習後、進んでポスターを作成し地域に貼ったりゴミを拾ったりと行動に移す児童が見受けられました。子どもの内面に働きかけ、意識を高めた成果の表れだと思われます。
社会科「くらしをささえる水」の学習、特別活動、道徳の学習を「水の勉強」ということで総合的に取り扱いましたが、子どもたちは白然に意識が高まり、実践化・態度化へと結びつき、効果的な指導ができたのではないでしようか。
しかし、1時間扱いとしては内容が豊富で、また教師も先を急ぎすぎたのでじっくりと考える時間が少ないようでした。内容について、もっと検討する必要があると思われます。
「心」で感じたことを「行動」に移すのは難しいことです。継続的な働きかけや活動を狭い学校の中だけにとどめず、家庭や地域の人々と連携し、積極的に多様な学習活動を展開していく必要性を感じました。
文献
千葉県環境部二環境学習ガイドブック、P.144〜148、千葉県環境財団(1994)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|